南国フィリピンのドゥマゲッティへの親子英語留学、移住サポートをしています、DEECの増田です。
今回は、日本とフィリピンの【法律やルール”の違い、そして私たちが現地で体験したちょっと驚きつつも学びのあった「トラブル対応」】についてお話しします。
■ 「そんなアバウトで大丈夫なの!?」と驚いた移住初期
日本での暮らしに慣れていた私にとって、
フィリピンに来て最初にカルチャーショックを受けたのが「ルールのゆるさ」でした。
電気工事の申請も、水道の契約も、ビザの手続きも、
「いつ終わるかわからない」「誰が担当かわからない」なんてことは日常茶飯事。
例えば、私が初めて長期ビザの延長をしたときのこと。
必要な書類を全部そろえて移民局手続きをお願いしていた弁護士事務所に行ったのに、
カウンターで言われたのは、「あ、ごめん、今は担当がランチ休みです」
え…それだけ?代わりの人いないの?と、内心プチパニック(はっきり言って切れた!)。
しかも、「1時間後に来てくれたら、たぶんいると思うよ〜」とニコニコ。
日本なら「予約時間を守ってるのに!」と怒るところですが、
フィリピンでは、その場の流れや人の都合が、ものごとの優先順位に勝るんです。
まあ、日本が特別なのかもしれません((笑))
■ トラブルは、いつも人で解決される。
でも面白いのは、書類やシステムはゆるいのに、人のつながりは本当に強いということ。
たとえばある日、子どもたちと市場で買い物をしていたら、
長女がちょっとした段差で足をくじいて泣き出してしまったことがありました。
すぐに近くにいたおじさんやおばさんが駆け寄ってきて、
「大丈夫か!?」「水持ってこい!」「ここの奥さん看護師だよ!」と即座に対応。
まるで地域の小さな救急隊みたいなチームワーク。
日本なら、まず救急車を呼ぶか、施設の責任者を探して…と順番を踏みますよね。
でもフィリピンでは、「とにかく今、目の前の人を助けよう」という反応が早い。
法律やマニュアルが整っていないからこそ(あるのですが、日常の機能に疑問あり)、人間力で対応する文化が根付いていると感じました。
また前記したカトリック的な(助け合いの精神)が生きているのかもしれません。
■ 法律はゆるい。でもそのぶん「心」で解決する力が必要
もちろん、緩さゆえに困ることもたくさんあります。
・契約書の内容が曖昧だったり
・「言った・言わない」のトラブルが起きたり
・裁判や警察沙汰になると、解決までに何年もかかったり…
*実際私も金銭トラブルで8年裁判中ですが、まだ未解決(笑)
日本のように、法整備や制度がきちんとしている国に慣れていると、
正直「なんでこんなに適当なんだ…」と思うこともしばしば。
でも、だからこそ私たち増田家が学んだのは——
「自分の言葉で伝えること」
「相手を否定せずに交渉すること」
「冷静に話し合う力」
*大切なことは契約書で書面化する(アグリーメントレターなどを最低でも)
これは、子どもたちにとっても、すごく大切なスキルだと感じています。

■ トラブルが教えてくれる「人と人」の距離のちょうどよさ
ドゥマゲッティでは、地域の人同士のつながりがとても強いです。
・家の前を掃除していたら、見知らぬ人が「ありがとう」と言ってくれる
・学校で何かあれば、先生からすぐメッセージが届く
・役所でも、窓口のお姉さんが「あなた、前にも来たわね」と覚えていてくれる
これは、日本ではなかなか味わえなかった距離感でした。
フィリピンでは、正しさより温かさが勝つことがある。
それを理解してから、私たち家族も肩の力が抜け、トラブルに動じなくなっていきました。
基本的にはトラブルやもめごとに発展しないように、良い意味で(許す)ということを基準に生活するのが理想です。
■ 留学・移住を考えるあなたへ:ルールの違いを楽しめる心を(許す力)
フィリピンに来ると、日本の常識はあまり通用しません。
でも、それを「不便」「不快」とだけ捉えるのはもったいない。
ルールがゆるいぶん、人が人を助ける力が強い国です。
そして、その違いを知った時、あなた自身やご家族のコミュニケーション力や柔軟さ(許す力)は大きく育ちます。
トラブルは避けたいもの。
でも、トラブルの中にこそ、人と文化の深い理解がある。
私たち増田家も、数々の小さなトラブルを笑い話に変えてきました。
次は、あなたとお子さんが、その“違い”を一緒に楽しむ番かもしれません

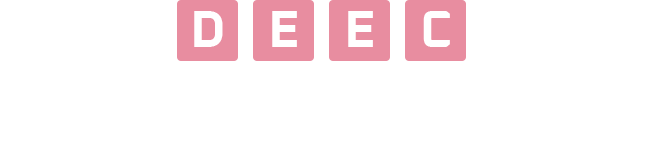


 戻る
戻る