こんにちは、ドマゲティ英語留学&移住センター(DEEC)代表の増田です。
今回は「授業についていけないときのサポート体制をチェック」というテーマで、DEECでの実例を踏まえて、「子どもが授業でペースを落としたと感じたときにどんな支援があるか」「親として何を確認すべきか」をまとめます。
1.公的制度・国際校におけるサポート体制の標準
まず、フィリピン教育省(DepEd)や国際教育機関が示している「授業についていけない子どものための支援」の標準を確認します。
DepEd の Revised K to 12 カリキュラムガイドラインでは、英語が母語でない生徒に対して EAL(English as an Additional Language) や補習(Remedial Classes)を用意するよう指導されています。特に低学年で言語理解に遅れが出る場合には、小グループでの支援や母語・英語併用の指導が認められています。
*上記は、インター校ごとにさアポートの違いがあるので直接確認が必要です。
インター校の基準ガイドライン(たとえば International School Manila や Nord Anglia など)にも、「学習支援(Learning Support)」「特別教育ニーズ(Special Educational Needs, SEN)」のクラスやアシスタント教師を設け、教科指導と語学指導双方で理解度を補う体制があります。
公式ウェブサイトでは、遅れた単元の補習、放課後支援、小規模グループでの追補授業などを明記している学校があります。
英語教育研究では、「初期の理解のつまづき」放置が後々の学業・英語力に影響を出すため、できるだけ早期にサポートを始めることが推奨されています。教育心理学の研究も、「早めの介入(early intervention)」が自己効力感と持続的な学びにつながるとしており、学校・家庭両方の連携が鍵とされています。
2.DEECで見てきた具体的なサポート体制
DEECが現地でサポートをした中で、「授業についていけない」と感じた子どもがどう支えられてきたか、以下のような実例があります。
〇家庭教師・補講制度利用
Grade 5 の女の子で理科の実験の部分が難しかったケース。学校が提供する補講クラスで教師のフォローを受けつつ、DEECが手配した家庭教師と週1回の復習セッションを設けることで、実験手順・予想と結果の比較などを丁寧に学び、授業内容を追いつくことができました。
〇アシスタント教師のサポート
英語があまり話せないため教科の説明が理解しにくい生徒には、アシスタント教員が授業中にそばに付き、指示をわかりやすく言い換えたり、視覚教材(図・模型・動画)を補足するなどしてくれる学校もあります。こうした配慮で、子どもの混乱が減り、自分から質問したり授業に参加しようとする姿勢が見られました。

3.親としてチェックすべきサポート体制のポイント
子どもが授業についていけないと感じたとき、親として以下のような体制やポイントがあるかを入学前あるいは学校見学時に確認しておくと安心です。
〇EAL や Learning Support の有無
英語理解が遅れている子どもを補う専門の支援があるかどうか。学校パンフレット・見学・先生との面談で確認できる。
〇小グループ補習・放課後補講制度
授業時間外に復讐できる機会があるか。「補習クラス」「チュータリング」の時間帯・担当教師の質を訊いてみる。
〇アシスタント教師やバディ制度
教科理解が難しいとき、クラスにサポート役がいてくれるかどうか。余裕を持って質問できる環境かを確認。
〇授業教材・指示の言語サポート
視覚教材・動画・模型・図表などが活用されているか。教師が語彙を平易に言い換えるなどの配慮をしているかどうか。見学参観で「説明のしかた」を観察する。
〇保護者とのコミュニケーション体制
子どもの理解度・進捗について先生と定期的に面談できるか。学校が保護者に報告書や進捗レポートを出しているかどうか。
〇学習内容の予習復習サポート
授業前予習用の資料が用意されているか。家庭学習教材・オンライン教材を学校が推奨・貸し出しているかどうか。
4.公的・信頼校からのアドバイスと制度の実例
International School Manila (ISM) の “Learning Support Program” ページには、授業でつまずきが認められる生徒に対して「介入プラン (Intervention Plan)」を作成し、家庭教師や EAL 教員による補習、小グループ形式のサポートを行っていることが明記されています。これは、学校側が早期支援を制度として設けていることを示しています。
また British Council の報告 “Supporting Learners in International Education” でも、授業についていけない子どもを助けるためには、「教師の柔軟な対応」「理解度に応じたペース調整」「家庭との協力関係」が重要であり、それが生徒の学業成功に繋がるとされています。
いずれにしても、学校見学などで事前に現場確認が大切です。
5.DEECとしてのアドバイス:親ができるサポート
授業についていけないと感じたとき、親としてできる具体的対策をいくつかご紹介します。
〇早めの発見
最初からスラスラとできる子供はいません。
授業後や宿題時に「理解できていない様子」がないか注意深く観察ししてみましょう。
子どもから「わからない」「ついていくのが難しい」と言う前でも、プリント・ノート・宿題のパフォーマンスでサインが出ることがあります。
〇先生とのコミュニケーションをとる
担任や EAL 教員に遠慮せずに「どこでつまずいているか」「家庭でのフォローはどうすればいいか」を相談する。具体例を持って行くと理解がスムーズです。
〇家庭学習で補強する
授業で学んだ内容の予習復習・語彙強化・問題演習を家庭で取り入れる。視覚教材を使ってわかりやすくする。
〇外部リソースを活用する
オンラインの補習教材・家庭教師・学習アプリなどを利用する。必要なら DEEC のようなサポートセンターの協力を得る。
当センターでは、家庭教師の紹介(予約スケジュール制)もサポートできます。
〇心理的な支援を忘れずに
ここが一番大切なところですが、「自分だけ置いていかれている」と思わせないように、褒める・励ます・小さな成功を積む。子どものモチベーションを保つ環境を作る。親としても焦らず長期的視点を持つこと。
6.まとめ
授業についていけないと感じるのは決して珍しいことではありません。しかし、適切なサポート体制が学校に整っていれば、子どもは遅れを取り戻し、自信を持って授業に参加できるようになります。
必要であれば、見学同行の際にこれらのポイントを回るご用意できますので、いつでもご相談ください。

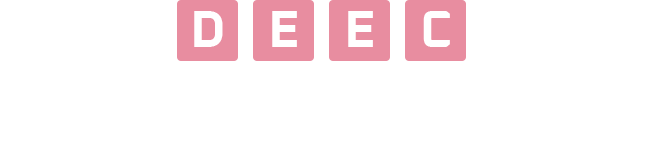


 戻る
戻る