こんにちは、ドマゲティ英語留学&移住センター(DEEC)代表の増田です。
今回は「インター校で育つ『自分で考える力』とは?」というテーマで、具体例を交えて解説します。
1.自分で考える力”クリティカル・シンキング/思考力)の公的な定義・研究
「自分で考える力」とは、単に答えを覚えるのではなく、情報を比較し・問いを立て・仮説を検証し・自分なりの答えや意見を導く能力を指します。フィリピンにおける教育研究では、この思考力は21世紀スキルの一つとして重視されており、DepEd(教育省)のカリキュラム改革でも強調されています。例えば、Science Laboratory の授業において、生徒が情報を選び取る力・実験を通して仮説を立て検証する能力を伸ばすことが、学習成果と強く関係するという調査結果があります。
以上を、東洋哲学的解釈と考える方も増えてきていますが、21世紀が心の時代と呼ばれていることでも納得がいきます。
また、学校教育において思考力を十分に育てるためには、教師の指導方法や授業設計の見直しが必要であり、単に記憶・再現型の学習だけではなく、問いを投げかける授業、議論や比較、問題解決型の学びが取り入れられることが求められている、という指摘があります。
さらに、国際校等では「How International Schools in the Philippines Teach Critical Thinking」の記事にて、以下のような戦略が実際に使われていると報告されています:探究(Inquiry)を奨励する、子ども自身に質問させる、問題を自分で解決する経験を持たせる、協働学習を通じて考えを共有・比較する、など。これらは「考える力」を育てる上で非常に効果的であるとされています。
2.インター校で「自分で考える力」が育つしくみ
インター校では、クリティカル・シンキングを育てるために、授業・学習環境・日常の活動などで次のような工夫がされています:
〇Project-based learning(プロジェクト型学習)
子どもがテーマを設定し(学校側の提示の場合も)、調べたり実験したり、プレゼンしたりする活動。子どもが自分で問いを立て、どうやって調べるかを考える過程があります。
〇Inquiry-based approach(問いかけ型授業)
教師が「これはどうしてこうなるだろう?」「この方法で十分か?」といったオープンな問いを投げ、生徒に考えさせる時間を設けます。間違えた答えも議論の入り口として尊重される文化があることが特徴です。
*この場合の生徒の回答は、個性が尊重され何が正しいという固定的な視点では評価されません。
〇協働学習(ペア/グループでの討論・共有)
多様な考えを持つ生徒と話し合うことで、自分の考えを再評価したり、新しい視点を得たりします。
〇実験・探究・ケーススタディ
理科実験だけでなく、社会科での現象観察や歴史比較など、現実世界の事例から学ぶ機会があります。
〇定評のある評価方法
テストだけでなく、プレゼン・プロジェクト提出・ディスカッション・ポートフォリオなど、生徒が自分で考えたものを表現する評価が多いです。

3.DEECで見た「自分で考える力」が育った実例
当センターが支援した実際の親子留学家庭で、「考える力」が伸びたと感じた具体的なケースをいくつかご紹介します。
〇ケースA:植物生育プロジェクト
小学3年生の子どもが、校庭で植物を育てるプロジェクトに参加。最初はどの土が適しているか・水やりの頻度はどうかを先生が示す形式でしたが、次第に子ども自身が「この土は水がたまりやすい」「この時間帯の光が強いから朝に水をやった方がいいかもしれない」など自分で観察と仮設を立て、実行・比較するようになりました。そのプロセスを通じて、「なぜそうなるのか」を考える力がついたと、親御さんも驚かれていました。
〇ケースB:歴史と比較文化の授業
中学年で、自国・周辺国・他大陸の歴史的事件を比較する授業がありました。たとえば、日本、フィリピン、イギリスで社会制度や法律の歴史を比較。「なぜこういう社会制度ができたのか」「気候・資源・支配の歴史が違うからではないか」など子どもからの発問が出て、それをクラスで討論する時間がありました。子ども自身が資料を探し、意見をまとめることで、単なる暗記でない思考が育ちました。
〇ケースC:日常生活での問題解決(高校生)
学校でのクラブ活動中に、予算を組む活動やイベント企画がありました。例えば、演劇クラブで舞台背景を作る際、「どの材料をどこで買うと安いか」「どの道具は繰り返し使えるか」などを話し合うことで、「コスト意識」や「効率を考える力」が自然と磨かれました。
4.公的/研究から見た効果:思考力の持つ力
Science Laboratory 授業での研究では、フィリピンの中学生がクリティカル・シンキングの観点で、情報の評価・実験設計・仮説検証に関して能力が高い生徒ほど、学業成績・授業参加度・将来的進路の選択肢の幅が広がるというデータがあります。
*生活実学が重視されます。
また、研究「Critical thinking skills and study skills as the determining factors in academic success of senior high school students」(2025年)の調査でも、思考力(Critical thinking skills)と学習スキル(study skills)が学業成功に有意に関連していることが示されています。
これにより、思考力は成績や将来の進学・キャリアに直結する力であることが実証されています。
5.ママとしてチェックすべきポイント
子どもが「自分で考える力」を育てる環境を引き寄せ、家庭でも支えるための具体的なアドバイスを以下にまとめます。
〇学校選びで「探究型」・「プロジェクト型学習」があるかを確認する
見学の際に、「子ども自身に問いを立てさせる授業」「実験・比較・討論」がどれくらいあるかを先生に聞くと良い。
〇家庭でも日常の問いかけを増やす
「どうしてこう思うの?」「他にどんな方法があるか」「これが正しい・最善かどうか考えてみよう」という会話を日常に意図的に入れる。
〇間違えることを恐れない環境を作る
子どもが思ったことを言ってみて、それが間違っていても安心できることが大切。「間違いは学びの一部」ですという言葉や態度を親が示す。
*親があまり固定的な解答だけを先に持たないことが効果的です。
〇多様な教材・体験を取り入れる
本・記事・歴史物語・科学実験キットなど多様な素材を使って考える機会を増やす。図鑑やドキュメンタリーなども有効。
*遊びや観光体験などもとても有効な手段です。
〇授業後に振り返る時間を設ける
プロジェクトや実験の後、「何がうまくいったか」「何を他の方法でやってみたいか」を親子で話すことで思考の深まりが促されます。同時に何が楽しかったかも大切です。
6.まとめ
「自分で考える力」は、教科の中で知識を得るだけでなく、自分で問いを持ち・比較し・自分なりの答えを導く力です。インター校通学型では、探究型学習・プロジェクト・実験・討論などの機会が豊富で、この力が育つ土壌がしっかりと整っています。
DEECとしては、親子でこの力を意識して育てていくことが、子どもの将来の自信・柔軟性・問題解決能力につながると確信しています。

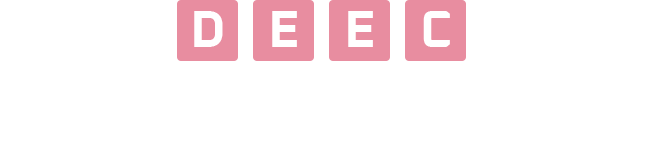


 戻る
戻る